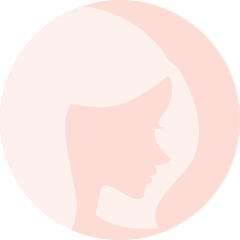ジャズ界の“公爵”、デューク・エリントン。平成人も楽しい聴きどころって?
- 2023年06月27日更新

『Take The "A" Train (A列車で行こう)』『It Don't Mean A Thing(スイングしなけりゃ意味ないね)』など、ジャズに詳しくなくとも知る人の多い、数々の名曲を手掛けたデューク・エリントン(1899~1974)。
ジャズだけでなく、ビートルズの楽曲や昨年ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの名曲『Blowin' in the Wind(風に吹かれて)』を演奏したりと、ジャンルにとらわれない彼の音楽は現代も多くの人に影響を与え続けている。

▲クリエイティブ・オフィス「司3331」
2016年10月15日、千代田区神田司町のクリエイティブ・オフィス「司3331(通称:ツカパー)」にて開催されたイベント「『エリントンの聴きどころ』~そうだったのか!デューク・エリントン~」(主催:「紙のジャズ」瀧澤主税)に参加。
平成人もゼッタイに聴きたくなる、“古き良き音楽”の魅力についてうかがった。

▲イベント主催の「紙のジャズ」瀧澤主税さん
主催の瀧澤主税さんは、長年ジャズ研究を行っている熱心な愛好家。
エリントンは、1960年代以降は日本でほとんど評価されず、国内リリースされていないアルバムも多いという。今回のイベントは、その現状に異議を唱えるための場でもあるそうだ。
1960年代┃若いトップ奏者たちをねじ伏せる、還暦を過ぎた公爵
 ジャズを聴くのにふさわしい、ビールで乾杯!
ジャズを聴くのにふさわしい、ビールで乾杯!
会場には『A列車でいこう』が流れ出し、瀧澤さんによる「デューク・エリントン・オーケストラ」の話がスタート!
「デューク・エリントンは、自身の名を冠したビッグバンド『デューク・エリントン・オーケストラ』のリーダーを務めました。1960年代の彼は60歳を過ぎ、もう音楽もマンネリ化しているように思えます。しかし、ライブでは相変わらず1930年代の代表曲『A列車でいこう』などを中心に、昭和の歌謡曲番組の司会のような丁寧なトークと綺麗な演奏で、いわゆる『芸能人』として振る舞っていました。実は、この時の彼はミュージシャンとして絶好調なんです。」

▲『The Popular Duke Ellington』
「1966年に発表されたアルバム『The Popular Duke Ellington』 は、いわゆるベスト盤。ただ、ぜんぶアレンジし直して再録音しているのが特徴です。このころのバンドのメンバーは古株と新人の老若混成で、スター奏者のジョニー・ホッジス(1906~1970)なども健在。ホッジスはアルトサックス奏者として、アメリカの音楽雑誌などに掲載された人気投票でも1位を取ることが多い人気者でした。

▲おつまみは持ち寄り
「1920年代にトランペットのスター奏者だったバッバー・マイリー(1903~1932)などは亡くなっていますが、その後継者のクーティ・ウィリアムス(1911~1985)が、マイリーの演奏を完璧に再現。このようにエリントンは、プレイヤーが変わってもサウンド自体は変わらない、『エリントンシステム』というものを長年にわたり作り上げていきます。」

▲『Money Jungle』
「エリントン自身もピアノ奏者で、1962年に発表されたアルバム『Money Jungle』 のなかに、特徴的な奏法が収録されています。このアルバム収録時のエリントンは63歳。当時のトップベーシストのチャールズ・ミンガス(1922~1979)40歳と、トップドラマーのマックス・ローチ(1924~2007)38歳と共演したアルバムです。ともにモダンジャズの第一人者ですが、エリントンは2人を上からねじ伏せるような音を奏でています。とにかく音量も大きくてびっくり。手数を多く魅せるような弾き方ではなく、1弾1弾『ガキンガキン』と音がするような、打楽器に近い印象で、リズムに徹し周り演奏者を自分のサウンドに引き込んでいます。
バンドも同じように、個性的な集団を率いながら、結局自身の強烈さと個性で“エリントンの曲”になってしまう。それが彼独特の能力です。周りが『俺が、俺が』と自己主張して演奏しても、エリントンは自身ですべてのサウンド構築を行い、ピアノひとつでまとめます。」
「妄想力」を働かせたエキゾチックな音楽。“奏者が主体”、逆転の楽曲制作
会場に流れる音楽がアルバム『The Popular Duke Ellington』収録の『Perdido』から『The Mooche』へと変わるころ、エリントンの一生が語られる。
「明治の終わりごろ、エリントンはアメリカの首都・ワシントンD.C.の裕福な家庭に生まれました。小学生のころピアノを習い始め、17歳でデビュー。20代でニューヨーク・ハーレムの高級クラブ『コトン・クラブ』と契約し、エリントン・オーケストラを始めます。
都会生れ・都会育ちで、ブルースが流れる田舎などにはエキゾチックな魅力を感じていたのでしょう。1928年発表の有名な曲『The Mooche』には、ドラムをドンドコ叩くジャングルサウンドにのせて、アメリカの農村部など未知の世界への妄想が表現されています。」

▲『Far East Suite』
「60年代、米国務省派遣親善大使として南アジア、西アジア、北アフリカ諸国を歴訪したことをきっかけに、1966年に『Far East Suite(極東組曲)』 をリリース。「極東」なのに、ジャケットにはインド(中東)のタージマハールが描かれており、これに収められた代表曲のタイトルも『Isfahan』と、なぜかイラン(中東)の古都の名前がつけられています。この辺の地理感覚、テキトーですよね(笑)。
こういった妄想力にあふれたエキゾチックな音楽は、アメリカのポップスでも基本的なスタイルだと思います。つまりアメリカのポップスを語る時にも、その元祖と言えるエリントンの話題は外せないんです。彼の音楽の影響力は広すぎて、どうしてもジャズというジャンルからこぼれてしまいます。ジャズ自体も、モダンジャズになるにしたがって4人~5人へと小規模化していくことが多いですが、エリントンは相変わらずビッグバンド。それも、ジャズファンがだんだん彼から離れていってしまう理由のひとつです。」

▲『…and his mother called him bill』は、バイセクシュアルであったエリントンの愛人であり、楽曲の共同制作もよく行ったピアニスト仲間、ビリー・ストレイホーン(1915~1967)の死を悼むアルバム
 「ただ、ビッグバンドでもソロの音を活かすのが、エリントン・オーケストラ。『曲があって演奏がある』のではなく、『奏者がいて楽曲がつくられる』という逆の発想なんですね。各ソロのメンバーが、まるで楷書のように、ひとつひとつの音をきちっと奏でる。メロディーもはっきりしていてキャッチーです。
「ただ、ビッグバンドでもソロの音を活かすのが、エリントン・オーケストラ。『曲があって演奏がある』のではなく、『奏者がいて楽曲がつくられる』という逆の発想なんですね。各ソロのメンバーが、まるで楷書のように、ひとつひとつの音をきちっと奏でる。メロディーもはっきりしていてキャッチーです。
ところが、口ずさもうと思っても、口ずさめないんです。楽器で演奏はできても、歌えない。歌との相性は悪く、ヴォーカルと共演している楽曲はいくつかあっても、目立った成果はほとんどありません。」
晩年のハンパないリズムへの追及。もし生きていたらラッパーに?
最後は、晩年のエリントンについて。

▲『LATIN AMERICAN SUITE』
「それでは60年代後半から70年代、本当の晩年の演奏についてお話しします。1968年リリースの『LATIN AMERICAN SUITE(ラテンアメリカ組曲)』。こちらは日本盤がありません。これまでと決定的に変わっているのはドラムの叩き方です。今までドラムについてどうこう言われることのなかったエリントンの曲でドンドコドンドコとリズム音が際立ち、すごいことになっています。」

▲『New Orleans Suite』
「さらに1970年のアルバム『New Orleans Suite(ニューオリンズ組曲)』 からは、ジャズ・オルガン奏者のワイルド・ビル・デイビス(1918年~)を入れ、音がエレクトリック化していきます。残念なことに、このアルバムを作っている途中でアルトサックス奏者のジョニー・ホッジスは亡くなってしまいます。それ以降、さらにチャレンジングになっていきました。例えばビートルズは、ジョン・レノンがいなくなったら成り立たないかもしれませんが、エリントン・オーケストラは、スターが消えても、エリントン本人が死んだ現在も、なお成り立っているという神がかった状況を作り上げています。」

▲『The Afro-Eurasian Eclipse』
「1975年発表のアルバム『The Afro-Eurasian Eclipse』 は、録音自体は1971年に行われました。これも日本盤はありませんが、エリントンの最高傑作と言い切って良いと思います。1曲目は『Chinoiserie』というタイトルで、表現しているのはエリントンの妄想の中国。曲の出だしのリズムがすごく難しく作られています。3拍子と4拍子を同居させて演奏することによって、この後に続くオーケストラの演奏の4拍子へ、そのまま繋がっていくんですよ。」

▲イベントスペースの端で眠っていたネコ(置物)
「多くのジャズメンが酒やタバコ、麻薬に溺れる一方、エリントンはスキャンダルも報じられず、まっとうな人生を送ったように思われます。ワシントンD.C.育ちのため、英語の発音はブロークンではなく声もしわがれていない、まるでCBSテレビのアナウンサーみたいにきっちりしています。
アルバムに収録されている『Chinoiserie』の演奏の前にはエリントンのクリアな発声でメディア論について語られた音声が入っています。曲の前にそれを2分も。こんなことを唐突に冒頭に入れる感覚、やっぱり彼はどこかぶっ飛んでいるように思います。品行方正で良識があり、なかなか自分の内面を人に語ったりしないと思われていた彼が、「オヤッ、ひょっとしてこの人も実は電波系なのでは?」という疑惑を持たせます。事実、エリントンの音楽をリスペクトしているジャズメンの大半が電波系だったり?(笑)」

「エリントンがもっと長生きしていたら、PCを使って1人で楽曲を作っていたかもしれません。2016年に亡くなったアメリカのミュージシャン、プリンスと共演もしていたでしょうし、Youtubeにおもしろトラックをいっぱいアップロードしていたんじゃないでしょうか。彼にとってみれば、ジャズを選んだのはたまたまだったんです。彼が音楽を始めたころの最新のジャンルがジャズだった。もっと生きていたら、ヒップホップもやっていたと思います。トラックメーカー兼ラッパーになっていたかもしれませんね。」
編集後記
毎年ノーベル賞候補に名前のあがる作家・村上春樹も、自著『ポートレイト・イン・ジャズ』の中でエリントンについて語っている。「天才というのは往々にして短気でせっかちで短命なものだが、デューク・エリントンはその才気溢れた人生を、まことに優雅に、まことにたっぷりと、まことにマイペースで生きた」。しかし今回の話を聞くと、優雅と言うよりただ自分の音楽にストイックに生きた人のように思える。スキャンダルを起こさなかったのではなく、起こす暇さえなくハイペースで75年の人生を駆け抜けたのではないだろうか。まだ、彼の人生について学ぶべきことは多い。2017年2月5日(日)、高円寺のライブハウス・JIROKICHIにて、瀧澤さんによるイベント『そうだったのか!エリントン』の第2回目の開催も決定している。私ももう1度、足を運んでみよう。
(取材/平原学)
こちらもどうぞ
人気記事ランキング
24時間PV集計
-
![]() 「僕が暴力を振るったとでっちあげされた!」モラハラ夫が無謀な依頼→弁護士の正論に撃沈!警察沙汰に発展!?【姉貴のカス旦那52】2026/03/08
「僕が暴力を振るったとでっちあげされた!」モラハラ夫が無謀な依頼→弁護士の正論に撃沈!警察沙汰に発展!?【姉貴のカス旦那52】2026/03/08 -
![]() モラハラ夫「とりあえず妻を呼び出してください…嘘ついても何してもいいんで…」危険を察知した弁護士が取った行動とは!?【姉貴のカス旦那53】2026/03/09
モラハラ夫「とりあえず妻を呼び出してください…嘘ついても何してもいいんで…」危険を察知した弁護士が取った行動とは!?【姉貴のカス旦那53】2026/03/09 -
![]() 【お願い!ブロッコリー1株あったらコレ作ってー!】“笠原シェフ”の食べ方に「マジで無限だわ(泣)」「家族で争奪戦」うまみ爆発レシピ2026/03/08
【お願い!ブロッコリー1株あったらコレ作ってー!】“笠原シェフ”の食べ方に「マジで無限だわ(泣)」「家族で争奪戦」うまみ爆発レシピ2026/03/08 -
![]() 絶体絶命のカス男「言うこと聞いてりゃいいんだよ!!」負け犬の遠吠え炸裂…妻の一言で完全終了【姉貴のカス旦那51】2026/03/07
絶体絶命のカス男「言うこと聞いてりゃいいんだよ!!」負け犬の遠吠え炸裂…妻の一言で完全終了【姉貴のカス旦那51】2026/03/07 -
![]() 「病気は完治してる…?」真実を知った義母が激怒→「このバカ息子がぁぁぁ!!!」大説教でスカッ!【うちの夫は病人サマ㊳】2026/03/09
「病気は完治してる…?」真実を知った義母が激怒→「このバカ息子がぁぁぁ!!!」大説教でスカッ!【うちの夫は病人サマ㊳】2026/03/09 -
![]() 義父「お前のSNSはもう見たからな」すべての悪事が家族にバレて、顔面蒼白…。嘘つき夫、ついに完全終了!【うちの夫は病人サマ㊲】2026/03/08
義父「お前のSNSはもう見たからな」すべての悪事が家族にバレて、顔面蒼白…。嘘つき夫、ついに完全終了!【うちの夫は病人サマ㊲】2026/03/08 -
![]() 【お豆腐は"生のままドボン"が大正解!】ポリ袋入れて放置でOK!「なのに、このウマさよッ!」「いやこれすごいって…!」見たことないレシピ!2026/03/09
【お豆腐は"生のままドボン"が大正解!】ポリ袋入れて放置でOK!「なのに、このウマさよッ!」「いやこれすごいって…!」見たことないレシピ!2026/03/09 -
![]() 北川景子さんの夫DAIGOさんも作った!うますぎて腰抜かす…【"厚揚げ"はこの食べ方が最高だった!】「これはずるいって」やみつきになる食べ方2026/03/06
北川景子さんの夫DAIGOさんも作った!うますぎて腰抜かす…【"厚揚げ"はこの食べ方が最高だった!】「これはずるいって」やみつきになる食べ方2026/03/06 -
![]() アイボリーは即“在庫切れ”!「買えない」嘆く人続出…【ワークマン】学生さん「通学に愛用してます」「チープに見えない!」最強アイテム3選2026/03/06
アイボリーは即“在庫切れ”!「買えない」嘆く人続出…【ワークマン】学生さん「通学に愛用してます」「チープに見えない!」最強アイテム3選2026/03/06 -
![]() 【鶏肉がこうも旨くなるとは!】栗原はるみ先生が相葉ちゃんに披露!「これはクセになる」究極の食べ方2026/03/07
【鶏肉がこうも旨くなるとは!】栗原はるみ先生が相葉ちゃんに披露!「これはクセになる」究極の食べ方2026/03/07
特集記事
-
2025年07月31日
-
2025年04月18日
-
2024年08月09日PR
-
2024年05月02日
連載記事
-
2019年08月21日
-
2019年05月28日