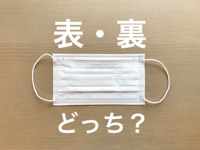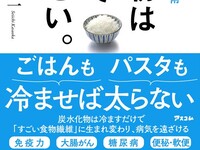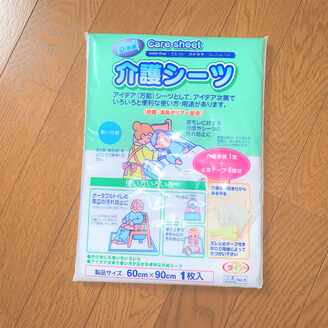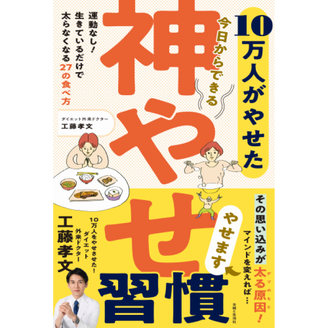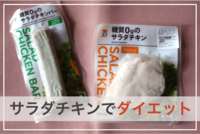1日3食は危険? 内臓脂肪や冷え性で起こる体の異変・・・今日からできる改善法
- 2025年05月14日公開

こんにちは、ヨムーノ編集部です。
ここでは、健康維持のために食生活や体脂肪、冷え性などヘルスケアに関する内容を紹介したヨムーノ記事の中からとくに人気だった記事をまとめてみました。
「一日3食とるのが体にいい」は、間違いだった

一日3食は、胃腸を疲れさせ、体の不調を招く
「一日3回の食事」が体に与えるダメージについて、一日3食の弊害として、最初に挙げられるのは、「胃腸をはじめ、内臓が休む時間がない」ということです。
人体において、食べものが胃の中に滞在する時間(消化されるまでの時間)は平均2~3時間、脂肪分の多いものだと、4~5時間程度であるといわれています。
また小腸は、胃から送られてきた消化物を5~8時間かけて分解して、水分と栄養分の8割を吸収し、大腸は、小腸で吸収されなかった水分を15~20時間かけて吸収します。
ところが、一日3度食事をすると、朝食から昼食までの間隔は4~5時間、昼食から夕食までの間隔は6~7時間程度となり、前の食事で食べたものが、まだ胃や小腸に残っている間に、次の食べものが運ばれてきてしまいます。
すると胃腸は休む間もなく、常に消化活動をしなければならなくなり、どんどん疲弊していきます。
しかも、年齢を重ねるにしたがって、消化液の分泌が悪くなり、胃腸の働きも鈍くなります。
すると、ますます消化に時間がかかるようになり、胃腸も疲れやすくなります。
アメリカの研究で明らかになった、「空腹」の効果
食べすぎによる害から体を守り、健康や若さを維持する、シンプルな方法。
それは、「ものを食べない時間(空腹の状態)を作ること」です。
近年、アメリカの医学界では、空腹(断食)と健康に関する研究がさかんに進められ、数多くの論文が発表されています。
以前から、「カロリー摂取を控えることが、さまざまな病気を遠ざけ、長生きにつながる」ことはわかっていましたが、これらの論文には、断食をすることが体重や体脂肪の減少につながること、そして、「糖尿病」「悪性腫瘍(がん)」「心血管疾患(心筋梗塞や狭心症など)」「神経変性疾患(アルツハイマー型認知症やパーキンソン病など)」などの予防に効果的であることが述べられているのです。
内臓脂肪がつく原因って?
内臓脂肪がついてしまう理由としては、「食事のバランス」と「運動不足」があります。普段から運動をする機会が少なく、食事が外食やファストフード、コンビニ弁当に偏ったり、飲酒の機会が多かったりする方は特に注意が必要です。
カロリーオーバーの食事
そもそも脂肪は、摂取カロリーが消費カロリーを上回ったときに、飢えなどの非常事態に備えて余分に蓄えられている、非常食のようなもの。
コンビニなどの普及でいつでも食事をとることができて、飢えることなく、高カロリーで脂質の多い食事が多い現代人は、内臓脂肪が極めてつきやすい環境にいるのです。
甘い食べ物をよく食べる

糖は体内に吸収されるとすぐにエネルギー源になります。でも、摂取した糖が多いとエネルギーで消費される分が追い付かず、残りは脂肪として体に蓄えられてしまいます。甘いものが好きでやめられない方は、摂った分だけ体を動かす必要があります。
睡眠不足

睡眠不足と内臓脂肪の因果関係については、さまざまな研究結果があります。乱れた睡眠習慣は体内時計を混乱させ、脂肪を蓄積させるホルモン分泌を促進するともいわれています。
運動不足

エネルギーを消費するのは筋肉。しかし、運動習慣がなく筋肉量が少ない人は、エネルギーを消費しづらく、内臓脂肪が蓄積しやすい体質になってしまっています。筋肉量を増やし、基礎代謝量をアップさせるためにも、運動する習慣をつけましょう。
自律神経の乱れ
自律神経は、内臓の機能や血流、代謝をコントロールしています。ストレスや不規則な生活で自律神経が乱れると、体内の脂肪の燃焼と貯蔵をコントロールしている交感神経の働きが低下し、脂肪がつきやすい体になってしまいます。
お酒の飲みすぎ
日本酒やビール、カクテルなど糖質を多く含んでいるお酒が多いため、エネルギーとして消費されない分が脂肪になりやすいだけではありません。お酒は食欲を高めるホルモンを分泌させるため、結果的に内臓脂肪の増加を促進する原因になります。
加齢による基礎代謝量の低下
何もしないでいると、筋肉は、年齢とともに自然に衰え、同時に基礎代謝量も落ちていきます。基礎代謝は、男女ともに10代半ば~後半にピークを迎えますが、成長のピークを過ぎると、体の維持以外のエネルギーが不要となります。
そのため次第に脂肪が燃焼されにくくなり、食事の内容が変わらなくても脂肪がつきやすくなってしまうのです。 【監修者紹介】渡辺尚彦[ワタナベヨシヒコ]
背中がやわらかくなると冷えが消える

肩甲骨まわりがやわらかくなると、冷え性も改善します。
冷え性とは、体内の熱が体のすみずみまで伝わらないことで起きる症状です。
冷えを感じる部分で多いのは、手足の末端、腰、下腹部など。なかには、全身で冷えを感じる方もいます。
冷えは万病のもとといわれ、そのままにしていると肩こりや腰痛、便秘などの体の不調の原因になります。女性の場合は、生理痛や不妊などにもつながるといいます。
また、体温が下がると免疫力が落ちるといわれ、風邪をひきやすくなったり、がんや心臓病などのリスクを高めることにもなります。
肩甲骨が硬くなることで冷え性を誘発する原因は、ふたつあります。
肩甲骨まわりの筋肉が硬くなることで血流が悪くなるから
熱は血液とともに全身に運ばれています。
つまり、血流が悪くなると、熱が運ばれなくなってしまうのです。それが、あなたの手足の末端が冷たくなってしまう原因かもしれません。
肩甲骨まわりの筋肉が硬くなってあまり使われなくなると、筋肉量が減り熱を生み出しにくくなるから
筋肉の役割はいろいろありますが、重要なもののひとつが体温の維持。
私たちの体は、筋肉が収縮することでつくられる熱によって守られているのです。
それでは筋力トレーニングといいたいところですが、肩甲骨まわりが硬くなっている人の多くは運動習慣がない人です。
そういう人が最初に取り組むべきことは、使われなくなっている筋肉をはたらけるようにすること。要するに、背中ストレッチで、眠っている筋肉を目覚めさせることです。
これまで使われていなかった筋肉が使われるようになるだけで熱生産力が高まり、さらに肩甲骨まわりがやわらかくなることで血流が良くなると、その熱を体のすみずみまで届けられるようになります。

「くらしをもっと楽しく!かしこく!」をコンセプトに、マニア発「今使えるトレンド情報」をお届け中!話題のショップからグルメ・家事・マネー・ファッション・エンタメまで、くらし全方位を網羅。
こちらもどうぞ
人気記事ランキング
24時間PV集計
ヘルスケア
-
![]() 12㎏やせた管理栄養士直伝「簡単ダイエット!挫折ゼロの成功4大ルール」2025/05/09
12㎏やせた管理栄養士直伝「簡単ダイエット!挫折ゼロの成功4大ルール」2025/05/09 -
![]() 血糖値を下げる食べ物とは?糖尿病にならないために今スグ心がけたいこと2022/10/20
血糖値を下げる食べ物とは?糖尿病にならないために今スグ心がけたいこと2022/10/20 -
![]() オートミールダイエットの正しいやり方!管理栄養士直伝「5分レシピ」3選も紹介2023/09/29
オートミールダイエットの正しいやり方!管理栄養士直伝「5分レシピ」3選も紹介2023/09/29 -
![]() 【医師監修】マスクの表裏・上下どっちが正解?正しい付け方・NGな付け方をおさらい!2024/07/31
【医師監修】マスクの表裏・上下どっちが正解?正しい付け方・NGな付け方をおさらい!2024/07/31 -
![]() 不調から脱した!ダルビッシュ有選手が唯一食べる炭水化物「冷凍の焼きおにぎり」を推す理由2024/04/05
不調から脱した!ダルビッシュ有選手が唯一食べる炭水化物「冷凍の焼きおにぎり」を推す理由2024/04/05 -
![]() 「ばんそうこうじゃなくって...」看護師がおすすめする【マツキヨココカラ】「ハイドロコロイドパッド」って?2024/04/05
「ばんそうこうじゃなくって...」看護師がおすすめする【マツキヨココカラ】「ハイドロコロイドパッド」って?2024/04/05 -
![]() 「ゆで卵ダイエット」1日何個が正解?管理栄養士に聞く【最新版】「簡単レシピ」と注意点2023/03/03
「ゆで卵ダイエット」1日何個が正解?管理栄養士に聞く【最新版】「簡単レシピ」と注意点2023/03/03 -
![]() 【ダイソー】介護シーツの使い方!食べこぼしや「おねしょシーツ」にもなる使い方2023/03/10
【ダイソー】介護シーツの使い方!食べこぼしや「おねしょシーツ」にもなる使い方2023/03/10 -
![]() 「ホンマでっか !? TV」出演医師【新提案ダイエット】「意外なアレ飲むだけ」デブ舌リセット2024/04/12
「ホンマでっか !? TV」出演医師【新提案ダイエット】「意外なアレ飲むだけ」デブ舌リセット2024/04/12 -
![]() 「サラダチキン」でダイエット!管理栄養士に聞いた「落とし穴」とアレンジレシピ2023/02/14
「サラダチキン」でダイエット!管理栄養士に聞いた「落とし穴」とアレンジレシピ2023/02/14
特集記事
-
2025年04月24日
-
2025年04月18日
-
2024年08月09日PR
-
2024年05月02日
連載記事
-
2019年08月21日
-
2019年05月28日